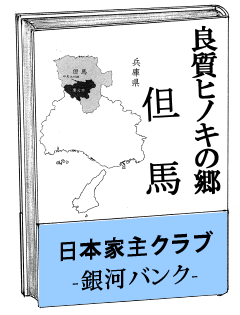銀河バンク
“不動産を15%安く取得する知恵”
■建売価格で注文住宅(や共同住宅)が実現できないか考えてみませんか。
注文建築は、建築の華であり夢です。なかには「面倒」だという人もありますが、チャンとしたコーディネーターがいて、設計(使い勝手)、仕様(メーカーや種類)、センス(色彩等)などを事前に打ち合わせさえすればなんでもないことなのです。
日本家主クラブは、そのような人の“であいの場”でありたいと考えています。
ご承知のように建売業界は現在、地域によっては買手市場となっています。事業主は利益を詰める等、販売価格引下げの努力をしていますが、次のような建売業としての余計な経費がかかってしまいます。
これらの諸経費は、通常10%~15%、時には15%~20%になることもあります。
注文住宅の場合は、このような経費の多くは不要です。この不要な部分のコストを活用してグレードアップし、注文建築というすばらしい夢の実現を考えてみてはいかがでしょう。
■実現するためには
1)業者と同じレベルの売地情報を直接得ること。
2)建物は、良きアドバイザーと相談して、工事する人へ直接発注すること。
◎売り出される建売マンションから選択するのではなく、希望者が集まり、企画から参加しての手造りマンションの実現だって可能です。
平成16年7月9日
■建売価格で注文住宅(や共同住宅)が実現できないか考えてみませんか。
注文建築は、建築の華であり夢です。なかには「面倒」だという人もありますが、チャンとしたコーディネーターがいて、設計(使い勝手)、仕様(メーカーや種類)、センス(色彩等)などを事前に打ち合わせさえすればなんでもないことなのです。
日本家主クラブは、そのような人の“であいの場”でありたいと考えています。
ご承知のように建売業界は現在、地域によっては買手市場となっています。事業主は利益を詰める等、販売価格引下げの努力をしていますが、次のような建売業としての余計な経費がかかってしまいます。
| ◎登記料 | 土地仕入時の所有権移転 事業資金借入のための抵当権設定 |
| ◎印紙税 | 土地仕入契約、借入契約、領収書等 |
| ◎不動産取得税 | 事業者が土地を取得して事業を行う場合、一定の条件を満たさなければ重複して納税することになります。 |
| ◎借入金金利 | 土地取得時から売却引渡まで(事務手数料等の諸経費含む)に発生するものです。 |
| ◎雑経費 | 施主が“事業を目的”として建設する場合は社会的な責任負担が応分にかかります。(自己使用目的の場合とは異なる) |
| ◎仲介手数料 | 建物竣工後、土地建物一括販売で売主からの支払手数料 |
| ◎リスク費 | 事業計画通りに販売できない場合の為のもので、次の様なものがあります。 |
| ・竣工後の金利(工事予定期間を超えた時) | |
| ・売却時期が遅れた場合の広告費の負担増 | |
| ・建物完成後の維持管理費 | |
| ・売れ残りによるダンピング損 |
注文住宅の場合は、このような経費の多くは不要です。この不要な部分のコストを活用してグレードアップし、注文建築というすばらしい夢の実現を考えてみてはいかがでしょう。
■実現するためには
1)業者と同じレベルの売地情報を直接得ること。
2)建物は、良きアドバイザーと相談して、工事する人へ直接発注すること。
◎売り出される建売マンションから選択するのではなく、希望者が集まり、企画から参加しての手造りマンションの実現だって可能です。
“優良物件探し上手”
平成16年6月16日
不動産は、とてつもない高額商品であることから、購入において一度失敗すると一生の不覚となってしまうこともあるほどです。このことについては、ほとんどの方が自覚の上で物件探しに取組まれているようですから、敢えてここで詳しい説明はしませんが、心構えとしては、1年以内とか5年以内というように、時間的な余裕を持って始めることが大切だと思います。
しかし反面、必要にせまられて目標を立て、充分な実力もありながら、なかなか実現できない方が以外に多くあるようです。ここでは、そのような方の典型的なパターン3つを提示してみます。ご自分で一度チェックしてみてはいかがでしょう。
パターン1 自分の希望が現実離れしてはいませんか? つまり、ないものを探していませんか?
パターン2 入ってくるお金をすべて消費にまわしてしまうことが、あたりまえになっていませんか?
パターン3 本当のチャンスに出合っても、決断を先送りしていませんか?
このような方は、事前に次のような点をしっかりと理解した上で、心の準備をしておかれることをお勧めします。
◎どんな物件でも、必ず良いところと悪いところがあるため、何を最優先するかを決めておく。
◎不動産取引は、日常消費商品の取引と異なり30%Off・50%Offのような取引は、正常な取引にはありません。逆に、もしそのような物件が目にとまったら、もう一度詳しい調査をすべきです。思わぬ落とし穴があるはずです。
◎買いたいと思う物件には、必ずライバルとなる相手がいることを理解しておく。
“逃がした魚が大きく見える”ものです。同じものが再度手に入ることがほとんどないことも不動産の特徴です。
◎購入は、予定の段階で家族や知人に相談することです。このことによって客観的に見た自分の実力や必要性が判断できて自信がもてます。
但し、相談する相手が、“ことなかれ主義”と申し上げると言葉が悪いですが、「とりあえず反対。」と、言われる方が以外に多いようです。ご自身の責任で決断する勇気を持たれることも大切です。
物件探し上手のポイントは何といっても“であい”です。
◎「いかに良いアドバイザーと出合うか」(ブランドとか、親切で良い人だけではダメで、実績と信頼が大切なのです)。
◎「いかに購入のタイミングが良いか」によって決まります。
日本家主クラブのアドバイザーは、そんな方々のお役に立てますよう努力を続けてまいります。